【ゲーム開発】私たちの風習や行動様式はゲーム作りのヒントになる

todoでございます。
本当はこのページはお盆の頃に書こうと思っていたのですが、今作っているゲームのアップデート作業に熱中するあまり1週間遅れになりました(笑) そもそそも8月のお盆自体が月遅れ盆なんて言われていますし、1週間は誤差といっても過言ではありません(過言)
お盆というと例年だと実家に帰ったりなどでごった返している時期ですが、2021年の今年は新型コロナの感染拡大もあり帰省がしにくい状況なのでお盆感はあまりなかったかもしれません。
こうした私たちの行動のベースとなる風習について考えてみると、ゲーム内のキャラクターや文化を作りやすいことに気付いたのでその点についてそれっぽくお伝えできればと思います。
日本の風習であるお盆といえば
お盆といえば日本に住んでいる人だったら馴染みが深いかもしれません。改めてお盆についておさらいしてみましょうか。
お盆は日本の夏に行われる先祖の霊を祀る行事のことです。会社にいる頃はお休みを取るための言い訳に使いやすい期間、なんて思ってました。全国的にお盆休みとして実施されるのは8/13から8/16が多いです。
お盆は元々旧暦の7月に行われていましたが、明治維新後、グレゴリオ歴が採用されて同じ7月でも旧暦との季節のずれが生じたことで、
「田んぼや畑の仕事と重なって大変なんだけど」
と全国的に支障もあったため、グレゴリオ暦で8月に行われるようになったとか。
東京などの都市部では田んぼの仕事もそこまで多くなかったからか、グレゴリオ歴でも7月のお盆になっているようですね。あとは季節的に東北でも7月が多いとか。
余談ですが私の実家の地域ではカンバと呼ばれる白樺の皮をお墓の前で焚きながら「おじいさんもおばあさんもこの明かりでおいでなさい」と歌う風習があります。迎え盆は「おいでなさい」で送り盆は「お帰りなさい」になっています。孫世代の小さな子供が集まっていると声も高いので明るい感じになりますが、大人世代が多いと低い声で歌うことになるので召喚の儀式めいた雰囲気が出てきます。
地域ごとにお盆の過ごし方や儀式の様子も異なるので、出身が異なる友人と違いを話し合ってみるのも新しい発見があるかもしれません。
風習によって生まれる行動
日本にいると、
「お盆には多くの人が実家に帰る」
という行動は当たり前のように感じますが、日本に馴染みのない人がこの時期に多くの人が移動しているのを見ると、
「なんで一斉に移動しているんだろう?」
と疑問に思うかもしれません。例えば日本に来て間もない海外の方が8月の中頃に一斉に休みを取る日本人を見ると「Why!?」とびっくりするかもしれません。風習を知っているのと知らないのとでは、その行動の意味を読み解き方が大きく異なります。
ここにゲーム開発のヒント、特にストーリーのあるゲームのヒントが隠されています。
人々の行動には理念や信念がある

人々の行動には、その行動を選択するに至るための理念や信念などがあります。ゲームを遊んだ際、ゲーム内のキャラクターの行動を見た時に行動単体を切り取って見ると、
「このキャラクターはそのように設定されたのだな」
と一歩引いた感じで見てしまいますが、例えば風習などに基づいた行動であることが分かると、現実の人間の行動様式とリンクする部分があるので行動に説得力が出てきます。上で挙げたお盆の例だと、ただ単に実家に帰っている人を見れば、
「この人が何となく帰りたかったんだな」
となりますが、多くの人が実家に帰るようなお盆という風習の存在を知っていると、
「なるほど、そういう時期だもんな」
と納得しやすくなります。
理念や信念というと個々人の考え方にフォーカスした感じになりますが、その理念も風習に裏打ちされたものであることが多いので、風習の要素をゲームに取り入れるのは説得力を増すための材料になります。
キャラクターの行動に説得力を持たせるメリット
キャラクターの行動に説得力を持たせるメリットはユーザーをゲームの世界に引き込めることです。
現実の人間がやっていること、つまり風習に基づいた行動をキャラクターが取ることで、そのキャラクターに親近感を抱きやすくなります。ゲーム内のキャクターが突飛な行動理念や行動パターンで動いていると、ユーザーの立場からすると「どういうこと?」と疑問が先に来ちゃうんですよね。ある程度ユーザーが理解できる行動パターンの場合は理解のために必要な労力が少なくて済むので、理解しやすさが親近感につながっていきます。
ここで、理念や信念、あるいはその裏打ちとなる風習は必ずしもユーザーが知っている風習と同じである必要はありません。私たちが知っているお盆と似たような風習で夏は家で蝋燭を灯す、みたいな風習があるかもしれませんが、大事なのは「風習に基づいた行動をしている」ことが伝わることです。
ゲーム内のキャラクターが現実の私たちと同じように風習に基づいた行動をしているのを見ることで親近感を抱き、よりゲームの世界のことを知りたくなったり、もっと探検してみたくなったりと、深く遊ぶためのきっかけになります。
モンスターの行動理念を考える上でも便利
風習に関しては人間のキャラクターだけではなくモンスター側についても考えておくと便利です。
例えばある種類のモンスターは冬になる前に、彼らの信仰する邪神に対して1年の感謝として人間を生贄に捧げる風習があったとします。なんて迷惑なモンスターだ! と言いたいところですが、私たちもお供え物として魚を祀ったりするのであまり責められませんね。そうは言っても、この風習のせいで人間の村には被害が出るので、ゲームに登場するキャラクターが人間であればモンスターを倒す動機付けになりますし、人間の立場であるユーザーにとってもゲームの進行と結びついているのでモチベーションとしては有効です。
あるいは少しアイディアを転がしてロマサガ風のフリーシナリオにして、
「そう かんけいないね」
と自由に振る舞ったり、逆にモンスターの味方をするダークなシナリオにしたりと風習から発生した行動に対するユーザーのアクションを広げていくこともできます。なんなら生贄としてプレイヤーキャラクターを捧げようとする村人と戦闘になるかもしれません。問題が解決したあとは「私が町長です」と何食わぬ顔でNPC面するキャラクターを出すのも良いでしょう。
モンスターの風習ひとつ考えておくだけで、モンスター自体の行動の他に村人の行動まで考えやすくなりました。
風習に基づく理念や信念は行動を生み、行動からは何らかの影響が生まれます。この影響に対してはゲーム内のキャラクターに加えてユーザー側の関わりが生まれ、ここに動機付けなども生まれてきます。
風習や行動様式はこうした状況を考える上で便利なので、現実の風習などをヒントに考えてみると良いと思います。
まとめ
今日のテーマはストーリーのあるゲームに関するものでした。元々RPGツクールからゲーム作りを始めたのでついついストーリーを重視してしまうのが私です。
小規模なカジュアルゲームなどではそこまでストーリーは必要ないかもしれませんが、ゲーム内のテーマに一貫性を持たせる上でストーリーは非常に有効なので可能ならゲームに取り入れてみるとグッド。
そのストーリーを作るひとつの要素としてキャラクターが生きている世界や地域の風習を考えてみるのは便利です。生き生きとした感じが生まれてきて行動にも説得力を出しやすく、ひいてはユーザーがゲームの世界に夢中になるための働きもあります。
ゲーム開発の攻略チャートを作りました!
-
前の記事

【ゲーム開発】オリンピックに学ぶゲームの情報を届けるための方法 2021.07.23
-
次の記事

【Unity】プロトタイピングでアイディアを素早く形にする開発 2021.08.22

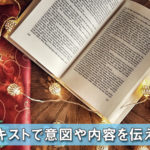
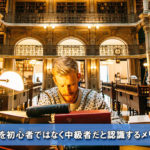


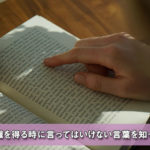
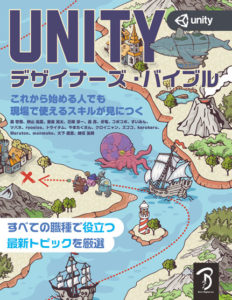





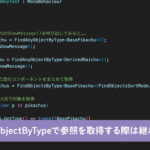

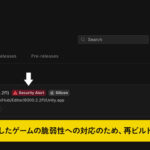

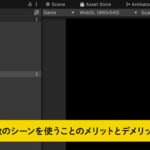

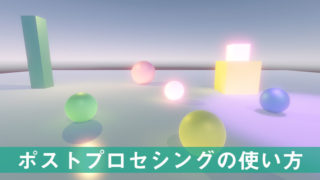



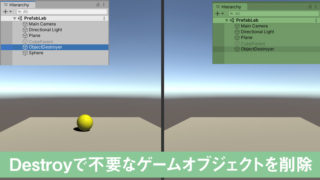



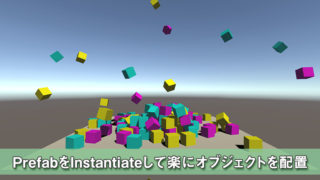



コメントを書く